グループホームと呼ばれる施設には
・障害者総合支援法の共同生活援助
・介護保険法の認知症対応型共同生活介護
があり、根拠となる法律も対象になる人も違います。ここでは
・介護保険法の認知症対応型共同生活介護 について触れていきます。
今回は主に人員:職員の数とかです。
人員と言ったけど、対象者についても一言
介護保険の施設なので、介護保険の認定を受けている人が対象になります。ただし、要支援1の方は利用できません。 要支援2(この場合は介護予防認知症対応型共同生活介護という名前のサービスになります)の方から利用可能です。
※読み飛ばしてもらっても結構です:なぜ要支援2から利用できるかは想像でしかありませんが、もともと介護保険ができた際に「要支援」という区分は無く。一番低い介護度は要介護1でした。平成18年ごろ、要介護1よりも軽度の方を早期に発見し、要介護度の重度化を防ぐ事を目的に、「要支援」という区分と地域包括支援センターの創設という流れだったような記憶です。その際要介護1の中で認知症が無い、もしくは軽度の方を要支援2と設定されました。 長くなりましたが、要支援2からグループホームが利用できるのはこういった歴史的な経緯も理由の一つかもしれません。
管理者
・3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する。(特別養護老人ホーム等での介護経験)
・認知症対応型サービス事業管理者研修を修了している。
・共同生活住居(ユニット)ごとに配置している。常勤専従だが兼務できる範囲あり。
兼務の範囲は介護事業の指定権限者(以下、自治体)により解釈が違うため、確認が必要だが
「2ユニットの管理者のみを兼務」することは可能であるとしている自治体もある。
しかし管理者が当該ユニットの他の計画作成担当者や介護職員を兼務しながら
他のユニットの管理者を兼務することは入所者への適切な処遇の観点からNGと判断される
可能性が高い。
計画作成担当者
・認知症介護実践者研修又は痴呆介護実務者研修基礎課程を修了している。(痴呆、久しく聞かない)
・保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する。
・1以上は、介護支援専門員である。:最大3ユニットのうち1人はケアマネ資格者であること
しかしながらこちらも兼務というか例外規定のようなものがあり、「併設する指定小規模多機能型
居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより、
当該事業所の効果的な運営を期待することができる。」という「まぁ、わかる」規定や
「利用者の処遇に支障がない。」という「許可の基準………?」といった規定がある。
・事業所ごとに専従で配置を基本とし、専従でない場合は以下要件を満たす事
兼務する職務が、当該共同生活住居における他の職務で、かつ利用者の処遇に支障がない。
R3年改定で介護支援専門員である計画作成担当者の配置について、
ユニットごとに1名以上→事業所(最大3ユニット)ごとに1名以上の配置に緩和されている。
2ユニットの計画作成者を担当して、プラスで他事業所の職種の兼任ができるかは自治体に確認して
ください。解釈が自治体それぞれで違うので…。
介護従業者
ここが一番複雑かも…
まずは日勤帯の人員(日勤帯が何時から何時までかは、そのグループホームで微妙に違いますなぜかというとルールに沿って事業所ごとに設定するからです。届出で使いますので、厳密に管理して下さい。計算したら人員不足にもなり得るので…)
・1人以上は、常勤である。
・日中の時間帯にユニットごとに、常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに
1以上配置(利用者の数は「前年度の利用者延数(人×日)」÷「前年度の日数」で割ったもの)
※医療法や、診療報酬上の入院料の看護師等の配置とは計算方法がちがいますので、日中のすべての
時間で入居者3:介護職員1にはなりません
(早出 通常 遅出等のシフトの組み方にもよるかと思います。)
・専従である。専従でない場合は
〇当該事業所に人員に関する基準を満たす介護従業者を配置している。
〇併設されている指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所において
人員に関する基準を満たす従業者を置いている。
〇兼務する職務が、当該事業所に併設されている事業所の職務である。
以上を満たす必要がある。
次に夜間及び深夜の時間帯の人員について
・ユニットごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤職員を1以上配置している。
・ユニットが3の場合、夜勤職員を2以上配置。しかしその場合は
〇同一の階において隣接していて利用者の安全が確保されている。必要がある。
その他に現場の人員ではありませんが、グループホームの管理者の上に開設者(代表者)というのがあり、そちらについても開設するに足りる資格や研修の受講が義務づけられています。例えば医療法人の理事長が開設者(代表者)になった場合は、実際の診療の現場に出ている医師の場合でも、認知症対応型サービス事業開設者研修を受講しなければならず、その日は自分のクリニックの診療を他の医師にお願いしなければならないなどの問題も発生するので大変です。
以上、今回はグループホームの人員について軽く触れてみました。
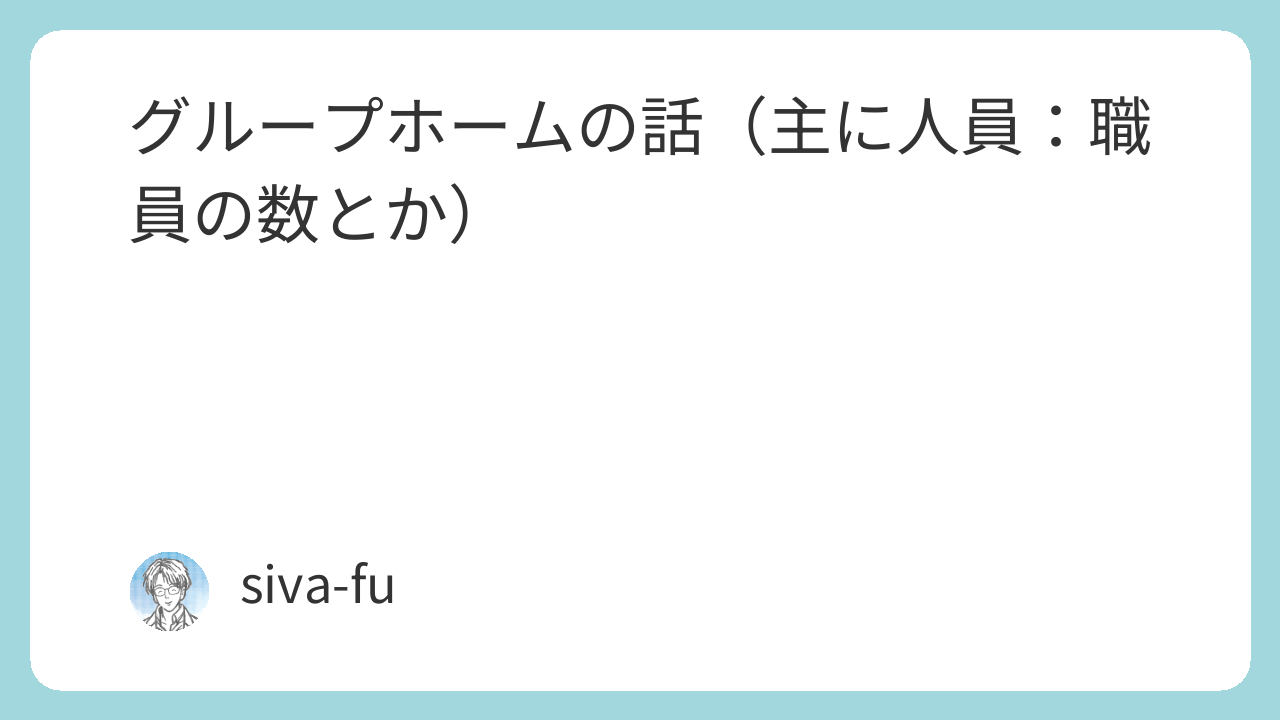
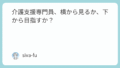
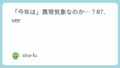
コメント