「ちょっと真面目な話、皆さんは介護保険というものをご存じだろうか? 「自分や、親が年を取って体が動かなくなってきたら、お世話になるもの。」 と漠然と考えている人はまだ良い方、むしろちゃんと興味をもって知ろうとしているといっても過言では無い(言い過ぎかもしれません(;^ω^))しかし現代の日本で天寿を全うしようとすれば必ずいつか向き合うことになる、それが介護保険である。」
ということで今日はまず、介護保険の話をしていきたいと思います。
介護保険の原型となる制度はドイツの法律だったと思います。日本で動き出したのは2000年あたりのことです。この辺りは制定の経緯になりますので実際の運用にはつながってきませんので飛ばしていきます。 介護保険制度ができるまではどうしていたのか?そう疑問に思いますよね?当然2000年になる以前も老人はいました、そして介護が必要な老人もいたのです!(当たり前) 当時は介護の制度としては、老人福祉法による措置としていわゆる老人ホームへの措置入所等が行われていました。介護保険制度が「入所契約」による入所となることに対して当時は市町村が行う「入所措置」だったのです。
介護保険制度ができる以前から日本は高齢化社会への突入が示唆されていました。原因はもちろん少子高齢化。高齢化の一因には医療の進歩や衛生、栄養状態の改善、進歩もあったと思います。その中で家族の構造も変化しました。祖父母、父母、子の三世代同居から父母と子の世代の増加、そして父母と子すらも別々に暮らすようになり……。介護が必要になった世代を介護できる土台も喪失してしまいました。その中で発生するさまざまな社会問題がありました。老々介護や家族の介護のために仕方なく退職する介護離職が出現し、「家族が家族を介護する」ことは社会的にも難しくなりました。昨今(2025年現在)ではヤングケアラーという問題も起こっていますが、それはいつか別の記事で触れるかもしれません。
ここから創設されたのが介護保険制度です。介護保険制度は色々な保険サービスを利用して自宅、もしくは施設で生活できるようになっています。どのようなサービスがあり、どのような施設があるかはどうすれば利用できるのかは後述しますが、基本的に保険サービスにおいてサービスをどのように組み合わせるか、どのようなサービスを組み合わせればより良い介護、人生が送れるか、その人らしい人生が過ごせるかについてはケアプランという計画を立てる必要があります。そしてその計画を作成するために「介護支援専門員」という資格も創設されました。
- 少子高齢化と長寿化で介護の量が増えてきた。
- 介護できる同居者は減ってきた。
- 介護保険制度が創設された。
- 介護保険制度のサービス利用には計画書(ケアプラン)が必要。
- ケアプランを作成するには専門的な知識とサービスの過剰、不足にならないバランス感が必要。
- 専門的な知識とバランス感を持つ資格として「介護支援専門員」ができた。
介護支援専門員の授業でやると怒られる?くらいざっくりとまとめてみました。
こうして生まれた介護支援専門員という資格ですが、国会の答弁で国家資格に上げられていたりしましたが、実際は都道府県知事からの免許という形で運用されており、5年の更新制という免許になっています。この更新性についても更新の費用や方法、意義を議論されるなど、資格としては悪く言えば不安定、よく言えば発展の余地がある資格だなぁといった個人的な感想です。
それではまた次の記事で会いましょう。
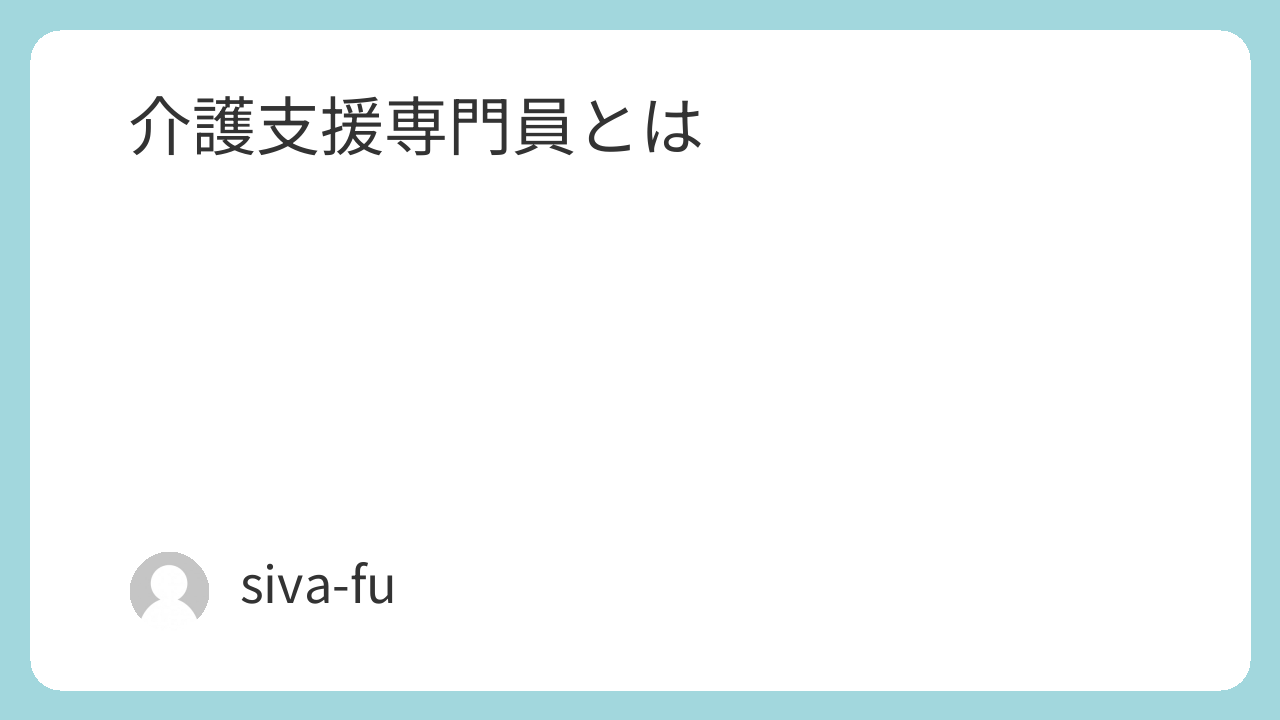
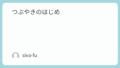
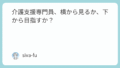
コメント